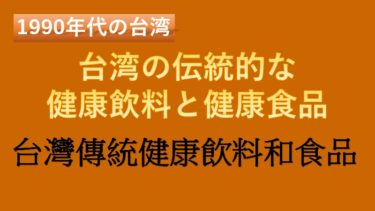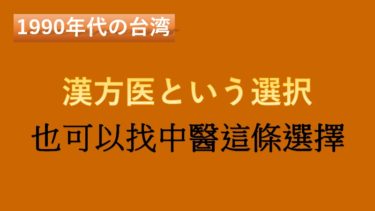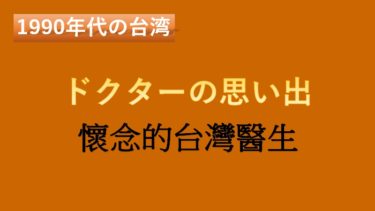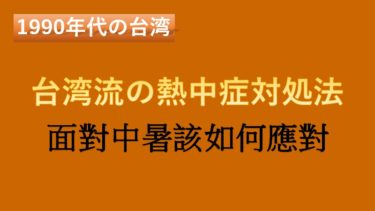できれば毎日を健康で過ごしたいものだが、残念ながら病気になることもある。そんなときに気軽に行ける病院や診療所があると心強いもの。
台湾の医療機関は日本とそれほど変わらず、安心して治療を受けられる。但し、日本語が通じないと心細くなるが、台湾では日本語ができる医師がいる場合もあり、そんな医師を見つけられたら、生活の安心につながる。
台湾は漢字圏なので病院にもかかりやすい
台湾の診療科目は日本に似て『外科』『内科』『小兒科』『皮膚科』等であり、時には『骨科』(整形外科)や『牙科』(歯科)のような例外がある他は、名称が殆ど同じで安心する。
漢方医という選択肢もある
台湾で医者と言うと、日本同様に西洋医学を習得した医師を指すが、東洋医学を履修した『中醫』(漢方医)も数は少なくなるが存在している。
漢方医も東洋医学をきちんと医学部で履修して国家試験に合格しているので、頼りになる存在である。また、患者にしてみれば、選択の幅が広がるメリットがある。
日本語を話す医師との遭遇
風邪で40度前後の熱が数日間続いたことがある。
見かねた妻に付き添われ、近所の町の診療所に行った。
待合室には長椅子が置かれ、片隅には患者達に読み回されたのだろう、よれよれに表紙の疲れた雑誌が乱雑に重なる。壁には病気予防やらのポスタ-が貼られている。飾り気なく簡素な診療所。
妻が受付で手続きをしている他は、人影はまばら。診察室からは医者と患者の話し声が漏れる。
受付を済ませた妻がやってきて、話しかけてきた。
「ここの先生はとても厳しくて、私は何度か怒鳴られたことがあるのよ」。
その一言で、縮み上がって、すっかり平静さを失った私に妻はにっこりと笑みを投げかけ「でも、いい先生よ」と言い足した。
できれば、ここに来る前に聞きたかった。
私の名を呼ぶ声が寒々した診察室に響く。遂に私の番が回ってきた。
通された診察室には老医師が一人、机に向かっていた。
かなりの御年配の御様子。
猫背気味だが、年のわりに体はがっしりと大きく、その上に猪首が乗る。
医師は、暫くペンを走らせていたが、それが終わると、回転椅子をくるりと反転させて、私の前に改めて向き直した。
卓上のカルテと私の顔を交互に見ながら、重そうな口を開いた。「あなた…〇△さんね」。
『えっ!?日本語!?』
混沌とした高熱の頭に母国語は優しく沁みる。
異国で病気になると、とかく心細くなるものだが、医者が日本語を解せると、自分が患者であることさえ忘れてしまうほど安心してしまう。
その後、触診と問診を重ね、いよいよ診断が下される。
「流行性感冒ですな」
そう聞いたとき、「日本語だあ。日本語だあ。それも流行性感冒だあ。」と、天にも舞い上がらんばかりに嬉しくなった。
もはや病名などはどうでも良いという心境に近かった。
薬の入ったビニ-ル袋を握りしめ、診療所を後にした。
帰りの道すがら喫茶店に立ち寄り、コーヒーに酔い痴れた。
高熱の病人が一体何をしているのかと、お叱りを受けそうだが、それほど安心感を得たという証左である。
すっかりくだんの医師のファンになる
数ヶ月後、今度は胃痛と吐き気に襲われ苦しみ、その先生のところを再び訪れると、やはり日本語で「ビールス性感冒ですな」と診断して頂いて、またまた嬉しくなってしまった。
この日には更にいろいろなおまけが付いて、「これは感冒と名前が付いてはいるが、実は感冒と言うよりも、ある種のビールス感染で、要するにあなたはビールスに感染したことになるのだよ」と一歩踏み込んだ解説付きだったから堪らない。
この時ばかりは吐き気さえなければ、帰り道に満漢全席でも食べたい心境だった。
異国で病を患うと、なにかと不安。
症状から病名が容易に自分で推測できるものならまだしも、得体の知れない病気だと、尚更のこと。
幸いにも、台湾には日本へ留学した経験のある医師も多く、日本語を解する医師も多い。
また、殆どの診療所の診療時間は昼休みを除けば、朝9時から夜21時まで。